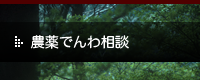閑談
リスクコミュニケーションに取り組んでみませんか?
1.はじめに
わが家の近くにゴルフ場があり、その脇に雑草がうっそうと生い茂る遊歩道があります。
先日通ったら、「蚊にご注意を! ○○市」と書いた紙が出ていて初めて、「ああ、ここは市道なんだ」と気付きました。「蚊の多い場所では次のことに気をつけて」として、長袖長ズボンや虫よけ剤の使用などを求めています。
でも、そんなふうに書かれると、だれもが思います。「蚊の多い場所自体は放置するの?」と。「そんなことを命じる前に、この生い茂る雑草を刈ってよ」とか「消毒はしたんでしょうね」「ボウフラがわく水たまりはないかしら」などと疑問が生じ、市への不満ばかりが募ります。
- 都内のある市の遊歩道に書けられていた注意(市の名称がわからないように、写真を修正しました)

これが、「デング熱発生を防ぐため、市は蚊の防除に懸命に取り組んでいます。市民の方々も、長袖の服を来たり虫除け剤を利用したりするなどして、蚊に注意してください」と書かれていたら、どうでしょう?
「なるほど、市も頑張っているんだな。でも、すぐに市道全部の草刈りなどできない、という事情もわかる。私たちもできることをやらなければ」とすんなり思えるのではないでしょうか。
世間にはこのような、コミュニケーション不全に陥っている情報伝達が少なくないのです。本欄読者の皆さんが関係する施設やゴルフ場等では、蚊対策にどのように取り組み、利用者や周辺住民などにどう伝えていますか?
2.リスクについて語らなければならない場面は多い
現代社会では、リスクにかんする情報を市民に伝達する場面が増えてきました。デング熱しかり、火山噴火しかり。本欄読者の方々が直面している、どう非農耕地を管理して行くか、どういう場面で農薬をどのように使うか、というようなこともリスクの管理、制御であり、市民の理解を得ながら取り組むべきことがらです。
その際には、「この方法が正しいから従ってください、納得してください」ではなく、双方向のコミュニケーションを構築し、市民の疑問に応え意見やアイデアも取り込んで、市民が腑に落ちる形で実行する流れを作って行くことが、とても大事だとされています。
2014年3月27日に、文部科学省「安全・安心科学技術及び社会連携委員会」が、リスクコミュニケーションの推進方策という報告書をまとめました。リスクコミュニケーションは「リスクのより適切なマネジメントのために、社会の各層が対話・共考・協働を通じて、多様な情報及び見方の共有を図る活動」と定義されています。
さまざまな方法が提示されていますが、注意点として次のように書かれています。
ステークホルダー間の異なる意見や価値観の画一化を図り、一つの結論を導き出すことを可能にする手段と考えることは適当ではない。これを十分認識し、ステークホルダーが広く互いの立場や見解を理解し合った上で、それぞれの行動変容に結びつけることのできる「共感を生むコミュニケーション」の場となることを目指すべきである。
3.双方向のコミュニケーションで、信頼を得る
なぜ、こんなふうに双方向のコミュニケーションや共感が強調されるのでしょうか?
それは、さまざまな視点から意見を出し検討した方が、リスクに立ち向かう具体策をよりよいものへと高めて行ける、という意味合いがあります。が、もっと重要なことは、双方向のコミュニケーションが信頼構築の第一歩だからです。
現代の科学技術にかんする情報は複雑です。市民が、その複雑さをきちんと受け止めるには、まずは落ち着いて、前回説明したような「システム2」を働かせなければならず、それにはやっぱり関係者間の信頼関係、互いの経験や知見を尊重する人と人との結びつきが必要なのです。
信頼が生じるからこそ、耳を傾けよう、考えようという気分になります。そしてじっくり考えることで、リスク対応の複雑さや科学技術の価値が腑に落ち、信頼が人だけでなく技術自体へも向けられるようになって行きます。それが、市民も考えて意見を出し、もっとよい技術へと高めて行こうという動きにもつながります。
市民に「自分の頭で考えよう」という回路を動かし、好循環を産み出すために、真摯なコミュニケーションが絶対に必要なのだ、と私は考えるのです。
4.難しく考えないで! リスクコミュニケーションは日常のやりとりから
では、具体的な取り組みを、どのようにしたらよいでしょうか?
リスクコミュニケーションというと、行政や科学者、大企業が行うものだというイメージがあります。大勢が集まる場を設定して話し合う?
いえいえ、違います。私は、たとえば企業なら、日頃の製品や事業にかんして質問を受けて答えるような当たり前の行為が、リスクコミュニケーションの第一歩だと考えています。
私は、食の安全にかんする問題を取材することが多いのですが、「なにか問題が起きたから理解してもらうためにリスクコミュニケーションを行って不安を解消しなければ」という発想で企画する行政や企業が多く見受けられます。
しかし、問題が起きた後で「情報を提供します。なんでも質問してください。意見してください」と言っても、市民の方は「どうせ、ごまかそうとしているんだろう」というような猜疑心が先立って、素直に情報を聞けません。吟味できません。
そうではなく、科学技術を用いて活動をする企業等が、日頃から誠実な姿勢示し、業務でよい効果を上げており、そのことを市民に説明し対話し協働を積み重ねて行く基盤があって初めて、なにかトラブルがあった時にも「いやいや、企業の事情も聞いてみようじゃないか」という気分になれます。
今、食品企業の中には、そのことを強く意識して企業活動を進めているところが出てきています。お客様相談室を重視し、「リスクコミュニケーションの最前線の場」と位置づけているのです。
お客様相談室には多様な相談が寄せられます。どの企業にお聞きしても、9割くらいは「この商品はどこで買えますか?」とか、「どのようにして食べたらよいですか?」というような、実際的な質問です。しかし、わずかですが、「この製品のこの成分が不安です」「どのような作り方をしているのですか?」「色が、いつもと違うように思うのですが」というような、製品の品質や安全性にかかわる問いかけが混じります。
その時に、消費者に根拠を示しながら答えて、関連資料を郵送したりする。わざわざ不安を訴えたり詰問してくれる、というのは、その企業への大きな関心の裏返しとも言える消費者行動です。だからこそ、ていねいに対応するのです。そして、そういう疑問が増えてくるようなら、「潜在的な不安が広がっているのかも」と捉えて、工場見学会を企画したり、ウェブサイトでの情報提供につなげたりします。
九州の生協で取材した話。組合員から、開封した製品にカビが生えた、という苦情が目立つようになりました。カビが生えるのは当たり前なのですが、そうした知識を持たない人が増えているそうです。そこから、組合員がもっと微生物についての知識を持った方が、クレームが減るだけでなく、組合員自身が家庭で食中毒防止をできる、と考え、組合員の勉強会を開きました。組合員らは、生協職員のサポートを受け、話し合って家庭での「チェックポイントリスト」を作り上げ、きれいなパンフレットになって組合員に配られました。
- コープ九州事業連合が、組合員による勉強会を経て作成したチェックリストのパンフレット
マンガでわかりやすく取り組みの意義を解説し、冷蔵庫の利用や調理の仕方など注意喚起している 

家庭での食中毒リスクは、実はかなり大きいと考えられています。日本の食中毒は、厚労省の統計では年間に患者が2〜3万人報告されていますが、これは、医療機関等から保健所に報告があり「食品が原因」とほぼ確定した人数に過ぎません。家庭での食中毒は把握されておらず、統計上の数字の100〜250倍の患者が発生している、との見方もあります。
そこまで考えると、生協のクレーム処理から発したこの取り組みは、立派なリスクコミュニケーションであり、それにより組合員は大きな利益を得ることになったとも言えます。
こうしてみると、本欄読者の皆さんもさまざまな場面で、リスクコミュニケーションに取り組めるのではないでしょうか。質問にていねいに答える。資料としてまとめて、問い合わせがあったらすぐに渡せるようにしておく。時には、施設やゴルフ場等に市民に来てもらい見てもらうイベント等も企画したら楽しいかもしれませんね。
農薬のリスクコミュニケーションであれば、「農薬について理解してもらおう」の前に市民との接点をつくりコミュニケーションを図り、「私たちは、こんなことを考えながら調べながら、動いていることを知ってください」という働きかけをする。情報公開というと、大層な取り組みに聞こえますが、市民は形式ではなく、「心」の方を敏感に察します。取り繕うのではなくオープンマインドで、日頃の皆さんの努力を市民に伝える。それは、冒頭でお示ししたようなお知らせの紙切れ一つから始まります。
普段の日常的な取り組みとし、頑張り過ぎず、長く続けて行く。それが、リスクコミュニケーションの大事な姿であり、信頼を獲得するための遠いように見えて一番の近道だと私には思えるのです。
5.参考文献
・ 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 安全・安心科学技術及び社会連携委員会報告書 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/064/houkoku/1347292.htm
・ 「リスクの社会心理学 人間の理解と信頼の構築に向けて」(中谷内一也編、有斐閣)
・ 「ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?」上下(ダニエル・カーネマン、早川書房)
6.著者の略歴
科学ジャーナリスト。1989年、京都大学大学院農学研究科修士課程修了(農芸化学専攻)。毎日新聞社に記者として10年間勤めたのち独立。食品の安全性や生産技術、環境影響等を主な専門領域として、執筆や講演活動などを続けている。「メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学」(光文社新書)で科学ジャーナリスト賞2008を受賞。2011年4月、科学的に適切な食情報を収集し提供する消費者団体「Food Communication Compass(略称FOOCOM=フーコム)を設立し、「FOOCOM.NET」(http://www.foocom.net/)を運営している。
デング熱にみる市民のリスク認識は……
1.はじめに
デング熱の患者が約70年ぶりに確認されて、テレビや新聞等で大々的に報道されています。厚労省が9月29日現在で確認した患者数は150人。多くの人が8月半ば、東京都立代々木公園やその周辺を訪れており、都は殺虫剤エトフェンプロックスを噴霧して蚊の駆除を行っています。
また、国もマニュアルを作成して全国の自治体に通知し、「国内感染事例が発生した場合、感染経路の特定を目的とした詳細な調査を開始するとともに、早急に媒介蚊防除対策を始めなければならない」として、代表的な殺虫剤を表として示しています。
2.農薬ではないのに、誤解される
表に並んでいるのは、農薬ではなく医薬品あるいは医薬部外品。農薬と成分は同じものも目立ちますが、農薬製品ではありません。皆さんよくご承知のとおり、学校や公園、街路樹等への農薬使用に付いては農水省から「住宅地等における農薬使用について」という通知が出されて、細かな遵守項目が決められています。社会の農薬使用への目線も大変厳しいものがあります。
ところが、混乱も出てきているようで、ジャーナリストの中には「農薬業界ウハウハ」などと表現する人もいました。同業者として、やりきれない思いがします。
それにしても、農薬散布にあれほど批判が集まるのに、デング熱発生という新しい“脅威”については、殺虫剤使用が問題になっている気配はありません。散布が多くの人にとっては、「当たり前の措置」とも受け止められたようです。農薬についてずっと取材してきた私としては、どうも釈然としません。
そもそも、デング熱ってそんなにリスクは大きいの? と考えるのです。デング熱は蚊がウイルスを媒介することで発症します。症状に幅があることが特徴で、感染しても発症しない人も多く、発熱や頭痛などの症状が出て1週間後に回復するのが一般的です。
ただし、デング熱に再感染すると、出血等が起きる重症型の「デング出血熱」となる確率が高くなる、とされています。
世界でデング熱にかかるのは年間約1億人。そして、約25万人がデング出血熱になります。デング出血熱になると、死亡者が出てしまいますが、医療レベルの高い国では、デング出血熱の死亡率は1%以下とされています。
ワクチンはなく、かかってしまったら対症療法しかありません。ですから、ひんぱんに感染するような環境にしてはいけない、というのはたしかです。十分な警戒が必要で、対策を講じなければなりません。しかし、ほかの感染症と比較すると、重症化率、死亡率共に高いとは言い難いのです。
日本では、同じように蚊が媒介する日本脳炎の影響を軽視できません。日本脳炎ウイルスに感染すると、1000人に1人は日本脳炎を発症し、発症した人の20〜40%は亡くなる、とされています。
- 50年前には2000人の患者が発生していたが大きく減った。1990年代以降は、数人程度で推移している。

出典:Pig Journal2006年9月号
1966年には2017人の患者が確認されました。殺虫剤使用や、ボウフラがわく水たまり等を減らすなどの蚊対策が充実し、予防接種(ワクチン)が普及したこともあり、患者数は減少。とはいえ、近年も年間に数人の患者が発生しています。
ところが、こちらは世間ではあまり話題とはなりません。患者数が減ったために警戒感が下がり、予防接種が集団接種から個別接種に切り替えられたこともあって、今後また流行が再燃するのでは、と懸念している人たちもいます。豚の体の中でウイルスが増殖し、その豚の血をすった蚊が人を吸血することによって、人にウイルスが移るとされています。そのため、養豚関係者は今も注意喚起に懸命です。
それに、デング熱や日本脳炎のようなウイルスの脅威を語るなら、日本では毎年死者が出る麻疹(はしか)や、妊娠期の感染が胎児に深刻な影響を与える風疹の方が、実は発症者が多く、大きなリスクなのです。ところが、そうした既存の感染症には注意を向けず、デング熱に大騒ぎ。社会のリスク認知にゆがみ、バイアスがあり、リスクの大きさに応じた対処ができていないのは明白です。
3.リスクの大きさを適切に受け止めて行動するのは、難しい
しかし、これが人というものなのです。以前は、こうした市民の動きに対して、科学者の多くが「科学的な情報を十分に提供して正して行く必要がある」と考えて実行していたのですが、市民の姿勢は変わりませんでした。
社会心理学の研究が進み、どうも人は、論理的、合理的には考えられず感情に走るもので、科学的な情報を提供するだけでは解決しない、ということが明らかになってきました。
さまざまな説がありそれぞれ興味深いのですが、ここでは二重過程理論をご紹介しましょう。人は、なにかが起きた時に即座に判断する、脳にとって低負荷で高速、かつ大雑把な思考で経験的なモードを持っているとされます。これがシステム1と名付けられています。そして、十分な時間や情報が与えられると、脳への負荷が高いけれどもより緻密に検討する分析的な思考モードにもなります。こちらが、システム2と呼ばれます。
デング熱のリスクと日本脳炎のリスクを考え、さらにほかの感染症を検討し、対策の優先順位付けをし、適切なリスク管理策として薬剤はどう使われるべきか、周辺にいる住民等への影響や、その場の生態系への影響等も考慮に入れながら考え判断し実行する。非常に高度な思考レベルを要求され、「システム2」を動かさなければいけません。
しかし、多くの人はじっくり考える前に「怖い」という感情が先立ちます。デング熱の患者が見つかり始めた頃、小児科には熱を出した子どもを連れて「デング熱では」と駆け込んでくる親が目立ったそうですが、親とはそういうもの。システム1が先立つものなのかもしれません。
研究によれば、日常生活において圧倒的に、システム1が優勢だそうです。さまざまな実験から、人が感情や先入観等に引きずられ、結果的に合理的とは言えない判断や行動をしてしまうことがわかっています。同志社大学心理学部の中谷一也教授は著書で次のように書いています。
人間は長い進化の歴史においておもに狩猟採集生活を営んできた。その中で次々に直面する意思決定場面では、粗くはあっても素早い判断が必要とされただろう。例えば、野生生物の気配を感じたとき、狩るか逃げるか、襲われた仲間を助けるか見捨てるか、目の前の少し濁った水を飲むかあきらめるか等々である。このような場面では経験的システムへの依存度が高くなる。「データを蓄積し、モデルを利用して、将来のリスクとベネフィットを確率的に評価する」という分析的システムを活用する判断は、人間が定住し、記録を保存し、文明を築くようになったせいぜい数千年前から機能するようになったにすぎない。
なるほど、です。こうしたことがあるので、多くの人はやっぱり、目先の話題に引きずられ、そのことのみを恐怖に感じ不安に駆られ、過剰な対策を求めてしまったり、わかりやすい、しかし間違った策に走ったりします。
4.市民にも、科学技術を活かした合理的な対策を理解してもらいたい
高度な教育や科学教育を受けたりしている人でも、往々にしてシステム1で判断してしまう、ということが、多くの実験で確認されています。私も、そしてこの欄をお読みの皆様も、合理的な判断に行き着かない可能性がある。
その一方で、システム2が働くのを助けてくれるのは、経験です。ほかのさまざまなリスクの要因、つまりハザードが私たちの暮らしにあることを知り、実際の対策をした時に、安易な手法に飛びつくと、トレードオフで別の新たな問題が発生したりすることを、身をもって知っている。「ここは、多角的に検討して判断しなければ」と促してくれます。
デング熱対策なら、殺虫剤を使用し医院に駆け込むだけでなく、ボウフラの発生源の制御、蚊の好まない環境づくりなど、総合的に取り組まないと意味がない、と本欄をお読みの方はきっと考えたに違いありません。そして、日本脳炎も注意しなきゃ、と脳裏をよぎったに違いありません。
その技術や思考をしっかりと活かしてほしい。ただし、一般市民はそんな努力を知る前にパッと判断してしまっているので、どうしても、両者の意思疎通を図るのが難しくなり、誤解も生じやすくなってしまっている。私はそんな構図を描き、リスクコミュニケーションの難しさを感じます。
科学研究が進み、技術が発達し、わかりやすい判断では解決できなくなっているけれど、人は本来的にその複雑さにどうしても目を背けたくなってしまう。だれが悪い、というわけでもないのです。
しかし、現実には科学技術を活かして合理的な策を講じて行く必要がある。医薬品や医薬部外品としての殺虫剤や農薬としての殺虫剤の意義や正しい使い方を、市民にもわかってもらいたい。
水田や畑、美しい松が連なる光景、整備された緑地……。そこで、科学技術が上手に利用され、食料を生産したり健全なスポーツ環境を提供したり、私たちに安らぎを与えてくれたりしています。陰には、本欄をお読みの方々のような皆さんの多方面の努力があります。市民が、その苦労に感謝できる日をいつか迎えたい。ならば、どのようにリスクコミュニケーションを行ったらよいのでしょうか?
次回、国の報告書等もご紹介しながら、私見を述べたいと思います。
5.参考文献
・厚労省・デング熱について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever.html
・東京都感染症情報センター
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/
・国立感染症研究所感染症情報センター
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html
・ 「とっても危ない日本脳炎」(伊藤貢・日本養豚開業獣医師協会理事、Pig Journal2006年9月号 )
http://www.e-jasv.com/gijutu_pdf/sippei_15_ito.pdf
・ 「リスクの社会心理学 人間の理解と信頼の構築に向けて」(中谷内一也編、有斐閣)
・ 「ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?」上下(ダニエル・カーネマン、早川書房)
6.著者の略歴
科学ジャーナリスト。1989年、京都大学大学院農学研究科修士課程修了(農芸化学専攻)。毎日新聞社に記者として10年間勤めたのち独立。食品の安全性や生産技術、環境影響等を主な専門領域として、執筆や講演活動などを続けている。「メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学」(光文社新書)で科学ジャーナリスト賞2008を受賞。2011年4月、科学的に適切な食情報を収集し提供する消費者団体「Food Communication Compass(略称FOOCOM=フーコム)を設立し、「FOOCOM.NET」(http://www.foocom.net/)を運営している。
むしと関わって半世紀、特にむしから学んだこと
1.はじめに
時の流れは早いもので、小生が「むし」と関わって半世紀になる。
幼少の頃「むし」にはあまり興味がなかったが、みかん篤農家に生まれ、両親が必死になって害虫と戦っている光景を見て、大学では農学部応用昆虫学を専攻した。卒業後、民間会社の大正製薬㈱で衛生害虫の研究を11年間行い、縁があって母校の静岡大学農学部に助手として赴任した。無我夢中で新しい学問分野の芝草害虫に取り組み、気がついて見ると何と38年の歳月が流れていた。今に至って回想すると若い時代に「むし」を通して、多くの偉大な学者、大学教授、諸先輩に恵まれ、大きな財産となって鮮明に脳裏に浮かぶ。
2.衛生害虫と関わって11年
1962年大学3年生の卒業論文のテーマでミカンネコナカイガラムシ(Rhizoecus kondonis Kuwana)に初めて遭遇した。指導教官は土壌昆虫学の権威吉田正義博士(故、静岡大学名誉教授)である。この害虫はみかん産地静岡県三ケ日地区で猛威を奮い大きな被害をもたらした。この害虫の生態を解明するため、試行錯誤の末、室内飼育法(みかん苗木の水耕栽培装置)を考案した。後に茶樹水耕栽培の基礎となったと聞き及んでいる。
1964年、大正製薬㈱に就職し、防虫科学研究室(製剤斑8名、生物斑5名)に配属された。無知の小生は素晴らしい上司林晃史博士(元千葉県衛生研究所長)に恵まれ、11年間(1964~75年)徹底的に指導を受けた。林氏は小さな民間会社の研究員でありながら、数々の公的機関と共同研究を申し入れ、多くの業績を残した。
この時、小生は数々の著名な学者、大学教授に紹介され、充実した研究生活を過した。我々は衛生害虫(イエバエ、カ、ゴキブリ、ナンキンムシ等)を対象に家庭用殺虫剤を開発していた。当時主力の有機リン剤から安全性の高いピレスロイドに転換した。天然ピレトリン(輸入品)の他、アレスリン、フタールスリン、クリスロンが次々合成され、いち早くエアゾール製剤には即効性の優れたフタールスリンやクリスロンを、蚊取線香には熱安定性の高いアレスリンを使用した。研究では衛生害虫を対象に、ピレスロイド+共力剤による殺虫力増強メカニズムを解明し、林晃史氏は「殺虫剤の効力増進に関する基礎的研究―PYRETHROIDSに関する共力作用について―」で1973年、名古屋大学農学博士を修得した。1966年東京湾ゴミ処理場(第2夢の島)でイエバエの大発生が報道され、マラソン抵抗性イエバエの出現が国立予防衛生研究所安富和夫博士によって発表された。我々は今後ピレスロイド抵抗性イエバエの出現を恐れ、その調査を実施することとした。
先ずは以前除虫菊の栽培が盛んであった北海道名寄市に注目し、北海道内50箇所(元北海道衛生研究所長、長谷川恩博士)からイエバエを採集して、薬剤感受性を調査した。以後次々を共同研究が申し込まれた。神奈川県下9箇所(元神奈川県衛生研究所長森谷清博士)、高知県下48箇所(元高知女子大学教授、松崎沙知子博士)、台湾5箇所(台湾政府)、さらに東南アジア(インドネシア、ボルネオ、スマトラ、ニューギニア等)20箇所(故東京医科歯科大学長、加納六郎博士)からイエバエを採集増殖して、有機リン剤6種、ピレスロイド2種、有機塩素剤2種の薬剤感受性を調べた。この研究調査には約4年間を要した。当初予想したピレスロイド抵抗性イエバエは発見できなかった。しかし、国内と台湾のイエバエはマラソンに対して強い抵抗性を示し、北海道札幌市(札幌系統と名称)は、マラソンの散布暦がないにも関わらず超抵抗性(LD50=200ug/♀)を示した。また、神奈川県三崎市のゴミ処理場(スミチオン散布暦5年)から採集したイエバエ(三崎系統と名称)は超スミチオン抵抗性(LD50=80ug/♀、世界一)を示した。東南アジアでは有機塩素剤(DDT)によるマラリアコントロールが行われていたにも拘らず、高い感受性を示した。これら一連の報告は防虫科学36巻(1971)~39巻(1974)、Jap.J.Sanit.Zooℓvo.22(1971)、Jap.J.Trop.Med.Hyg.vo2(1974)に掲載した。
さらに小生は「イエバエの有機リン剤抵抗性に関する研究―特にfenitrothion抵抗性について―」で1980年、東京農業大学農学博士を修得した。
3.芝草害虫と関わって38年
1975年恩師吉田正義教授の要請により母校の助手となった。芝草害虫という全く新しい分野に挑戦することとなった。先ずは静岡県内7箇所のゴルフ場に誘殺灯を設置し、グリーンキーパーに依頼し、1週間毎に採集した昆虫をゴルフボールの空箱に入れ、宅配便で研究室へ送って頂いた。期間は5月~11月までである。見る見るうちに山積された採集箱を横目で見ながら、小生は朝から晩まで芝草害虫(それ以外の昆虫類)の仕分けに追われた。最初は昆虫図鑑を片手に悪戦苦闘したが、半年経過後、やっと一目で仕分けができるよになった。この苦労は後々の研究に大いに助けられた。
1970年以降全国的に次々ゴルフ場が造成され、特に侵入害虫シバツトガ(Pediasia teterrellus Zincken)や在来種スジキリヨトウ(Spodoptera depravata Butler)の芝草への被害が急増した。しかし、これら害虫の発生生態、防除法が解明されておらず、無計画に大量の殺虫剤が散布された。1980年代になると侵入害虫のシバオサゾウムシ(Sphenophorus venatus vestitus Chittenden)の被害が兵庫県、福岡県、沖縄県で発見され、1990年各都道府県病害虫防除所の調査により、関東以西の殆どのゴルフ場で被害が発見された。
今までの調査で印象に残った事項を少し紹介する。
1)暗闇に突如として現れたチビサクラコガネ(Anomala schonfeldti Ohaus)とオオ
サカスジコガネ(A.osakana Sawada)の大群
両コガネムシは生態的に共通点がある。我が国では関東以西の海岸砂丘、砂壌土地
帯に造成されたゴルフ場に生息し、成虫は6月下旬~7月中旬の夜間の一定時刻に出
現し、成虫は餌植物を摂食せず産卵する。1975年、静岡県磐田市の海岸沿線にある浜
松シーサイドGCの夜間調査の様子を述べる。遠州灘の海鳴りの音が遠くに聞きなが
ら、徐々に日は沈み丁度19時30分(照度20Lux以下)に突如として両種コガネム
シの大群に遭遇した。乗りつけていた自動車のフロントガラスを始め、我々の体にぶ
つかりながら芝生上1m程の所を数万~数十万頭の成虫が群飛する光景を呆然として
眺めていた。このドラマは僅か30分(20時)に終息し、芝地上に下りて盛んに交尾
が行われ、時間の経過と共に芝地に潜り姿を消して行った。このような光景は発生最
盛期間中毎日観察された。
両昆虫共に、海岸線沿いの草地に生育するイネ科雑草の根を食べて細々と生活して
いたものが、ゴルフ場の造成によって幼虫の餌植物は無尽蔵にあり、知らず知らずの
うちに増殖し大発生をもたらしたものである。即ち普通一般の昆虫が害虫化した珍し
い例である。
2)新設ゴルフ場におけるマメコガネ(Popillia japonica Newman)の大発生の再現
マメコガネは我が国が原産で、1916年日本から輸入したアヤメの苗に付着して北アメリカに侵入した。最初の発見はニュージャージ州リバートンであった。毎年のように農作物の被害は拡大し、1920年にはペンシルベニア州、1933年にはニューヨーク州、1941年には首都ワシントン州へ。現在は北はメーン州から南はジョージア州の20数州で毎年のように農作物(リンゴ、モモ、牧草、樹木など)へ多大な被害を及ぼしている。1926年USDAではマメコガネ研究所を設立、この虫の生理・生態、防除法(天敵やフェロモントラップ)など多くの研究成果が公表されてきた。静岡県駿東郡長泉町にある富士エースGCは開場(1979年)して5年目にはマメコガネの大発生を招き大騒ぎとなった。ゴルフ場増設以前は標高450~550m愛鷹山麓に位置し、人工ヒノキ林であった。従ってマメコガネは生息できる環境ではなかった。ゴルフ場造成に伴って日本各地から集めた芝生を張り、さらに美しい景観を保つため、6,000本の四季咲きのサクラを植栽した。芝生に付着した少数のマメコガネ幼虫が出発点として、成虫はサクラを摂食後、再び芝生地に産卵、僅か5年で大発生をもたらした。これは正にマメコガネが新天地北アメリカに侵入して爆発的に増殖、拡大した様子の縮小版である。
3)難防除害虫であるコガネムシ類の累代飼育法の挑戦
コガネムシ類幼虫は土壌昆虫であるため、土中の生息分布、生息密度及び越冬の様子など的確に把握することは困難である。また有効な防除剤もなく、難防除害虫とされていた。小生は身近にいるドウガネブイブイ(A.cuprea Hope)に着目し、年2回発生の可能性について検討した。一般に野外では3令幼虫は秋季に入ると土中深く潜り休眠し越冬する。実験室で温度処理によって休眠を誘導し、再び覚醒を促すこととした。幼虫の飼育培地は広葉樹腐葉土が最適で、25℃恒温室で孵化後の1令幼虫は僅か1ケ月で3令幼虫(最終令期)に発育する。3令幼虫に達して0日令、30日令、60日令及び90日令に分け、それぞれ10℃と20℃の低温に処理する。さらにその期間を10日、20日、30日及び40日として、再び25℃に戻す。その結果30日令を20℃で30日間低温処理後、再び25℃に戻した区は卵から成虫までに要する日数は181日(生育期間が約70日短縮)となった。ところが冬季に成虫が出現し急遽成虫の餌を探し回ったが見当たらず、そこで成虫の人工餌の研究に取り組んだ。基本的には成虫が好むイヌマキの新葉を風乾、粉末にしたものをベースとした。これに炭水化物、蛋白質、コレステロール、ビタミンB群等及び防黴剤(プロピオン酸)を添加し、寒天で固めた。この成虫の人工餌は天然のイヌマキの葉と比べ、①成虫の寿命(約2倍)②産卵数(約3倍)③孵化率(同等)であった。この結果、ドウガネブイブイは周年を通して大量飼育が可能で、しかもステージの揃った幼虫が大量に入手可能となった。このコガネムシ類の累代飼育法(応動昆1984)は世界で最初の研究であったと自負している。昨今、これら幼虫を使って、新しい防除剤が開発されたため、ゴルフ場からコガネムシ類の姿がみられなくなった。
4.ゴルフ場に散布された農薬の流出試験
1970年度中頃にゴルフ場造成のピークがあり、その後1987年、総合保養地域整備法
(リゾート法)が制定され、ゴルフ場は再び急増した。ゴルフ場の芝草管理用の農薬使
用量は増大し、河川などの環境汚染への懸念が広がり、社会問題となった。それを証明
する事件が1989年12月北海道のゴルフ場で発生した。雪腐病予防に散布した有機銅剤
が大雨により河川への流出が原因で、養殖魚の大量死亡事故が発生した。1990年2月
千葉県議会では沼田武知事が今後新規ゴルフ場への農薬使用全面禁止令を発令した。同
年5月国会においてもゴルフ場農薬問題が審議され、向こう3年間の時限立法を定め、
農林水産省は各都道府県に対して「ゴルフ場農薬適正使用基準のマニュアル作成」と指
導徹底させた。当時ゴルフ場で使用される農薬は非農耕地と同じ扱いであったが、芝草
生産も農作物生産と同じ扱いに変更した。芝草農薬は登録制となり、農薬取締法に基づ
いて農林水産省の管轄化とした。1989年、小生らはゴルフ場に散布された農薬が大雨に
よってどれ程流出されるかについて検討することとした。丁度、静岡大学農学部森林科
学科教授土屋智博士(専門:砂防工学)と遭遇し、協力を頂いた。土屋氏は降雨強度と
浸透強度の関係について、ヒノキ人工林とゴルフ場のラフ及びフェアウエイについて、
測定した結果を提供して頂いた。さらに表流水の測定方法についてもアドバイスを受け
た。
実験は1989年6月と9月、リバー富士CC甲斐コース№5のフェアウエイ1区1000
㎡を設け、6月はスミチオン乳剤を、9月はダイアジノン粒剤を散布した。散布後大型
スプリンクラーで時間雨量30㎜及び50㎜の大雨を降らせ、芝地からの表流水は下流部
に設置した1㍑転倒升に受け取り、初流、中流、終流に含まれる殺虫剤を分布した。結
果は殺虫剤散布直後に30㎜/hまたは50㎜/hの大雨では表流水に高濃度の殺虫剤が検出
された。当時、水文学において時間雨量50㎜は5年か10年に一度あるか否かといわれ
ていた。僅か20年後の昨今、時間雨量50~100㎜は日本列島至る所で日常茶飯事の出
来事であり、改めて地球温暖化の恐ろしさを感じる
多発する「ナラ枯れ」、蘖(ひこばえ)は生き残れるか?
1)カシノナガキクイムシの遺伝的タイプ
カシノナガキクイムシ(以下カシナガという)は日本海型と太平洋型の大きく2つの遺伝的タイプに分けられる。日本海型とは日本海側を中心とした本州日本海側、九州、奄美大島、徳之島、沖縄本島)に分布するタイプで太平洋型とは石垣島、紀伊半島南部、九州南部に分布するタイプである。カシナガが日本海型と太平洋型の2つの遺伝的タイプに分かれた経緯については分かっていないが少なくとも日本で種分化したのではなく、遠い昔に東南アジアで分化し、氷河期を挟んでそれぞれが別経路で日本に入ったと考えられているようだ。
日本海型のカシナガはナラ類の分布域、太平洋型はシイ・カシ類の分布域に生息する傾向があるので一見寄生樹種を選好しているようにも見える。しかし、日本海型のカシナガはナラ類もシイ・カシ類も加害して枯らすことから両タイプ間に寄主選好性の違いはないようである。ただし、このことがこれまで主に日本海側で発生していた被害が近年、寒冷地や高標高地への被害も含め太平洋側で被害が拡大している原因である。
林野庁が公表した24年度の全国28府県で発生したナラ枯れ被害量は約8万m3で前年度と比較して半減し、被害はどうやら終息の兆しを見せ始めた。
2)「カシナガ」と「ナラ菌」は「絶対的共生関係」、それとも「条件的共生関係」か?
本来、菌類の多くはキクイムシに随伴し樹木へと伝播され、分散を依存して生活する。ある種の菌類は、幼虫の栄養源としてキクイムシの生存に重要な役割を果たす(=絶対的共生関係)。ここではカシナガと酵母の関係である。一方、キクイムシの生存には寄与しないが樹木に対して病原性を有し、キクイムシの増殖に寄与する菌類もいる(=条件的共生関係)。
養菌性キクイムシは、基本的に「衰弱木」や「伐倒木」に穿入する。つまり、健全木には穿入しない。そうであれば「ナラ枯れ」の病原菌であるナラ菌(Raffaelea quercivora)の役割は一体何だろうか?ナラ菌が何のためにあえて衰弱した寄主の抵抗力をさらに低下させる必要があるのだろうか?強いてその必要があるとすれば樹体内に穿入したカシナガの大繁殖を可能にしたことであろう。つまり、カシナガとナラ菌はいわゆる繁殖戦略に寄与する条件的共生関係に共進化した。そのように考えれば本来樹木に対して病原性がないといわれているRaffaelea属菌が樹木を枯らす役割を担っていることも何となく理解できる。
カシナガに随伴してナラ菌が樹体内に侵入するとその応答として寄主は道管内に風船状のチロースを形成し、一部道管を閉鎖する。同時に寄主は組織柔細胞の変性・壊死を伴う過敏感細胞死という過剰なほどの生体防御反応によって多量の抗菌性二次代謝物質を生産しナラ菌を封じ込もうとする。しかし、どういう訳かこの生体防御反応はナラ菌には有効に働かないようだ。そのため寄主の抵抗力は著しく低下し樹体内に侵入したカシナガは一気に大繁殖を開始する。そして多数のカシナガの孔道によって通水機能を持つ道管が切断され、通水が停止して地上部が枯れるのであろう。
ちなみにミズナラやコナラ等はシイ・カシ類に比べて枯れやすいといわれている。それは上述したカシナガの遺伝的タイプにもよるが、これらの樹種はナラ枯れしないブナなどの散孔材とは異なり環孔放射材で樹皮のすぐ下の最近1~2年の年輪幅内の大径道管のみが通水機能を持ち、カシナガの孔道によって切断されやすい道管配列構造であることも関与しているのではないかと思われる。ただし、ここで気になるのはこのようなメカニズムで地上部が枯れたとして果たして地下部(根系)まで枯れてしまうのだろうか?蘖(ひこばえ)は生き残れるだろうか?ということである。
3)萌芽更新は可能か?
森林伐採後、切り株や根元から蘖(ひこばえ)が出て新たな森林が再生できるようになることを萌芽更新という。萌芽は、休眠芽で普通、葉で生産されたオーキシンによって発芽が抑制されているが、伐採や火災などで樹幹上部が消失したり、倒木によってオーキシンの抑制効果が消失し、発芽する。それなら「ナラ枯れ」で樹冠部が枯れても萌芽は発芽する。だが萌芽は新生葉が展葉して同化作用が回復するまでは親木の根から水分やミネラルを吸収し根に貯蔵されたデンプンや糖などの養分を使い親木に依存して生長していかねばならない。
図1に示すようにカシナガの成虫は地際部に集中的に穿入する行動習性があり、数は少ないが地下10cmの根株にも侵入する。したがって根株では地上部と同じようにナラ菌による組織柔細胞の変性・壊死が起きると考えてよいであろう。それは地上部より局部的かもしれないが形成層や篩部などの柔組織機能に影響するとなればことは重大である。つまり、篩部などの柔組織機能が低下すると根の貯蔵物質の萌芽への転流が阻害され、萌芽は生長しても展葉するまでに至らず枯れてしまうことになるからである。
根の貯蔵炭水化物が増加する時期は常緑広葉樹では、4~5月頃、落葉広葉樹では、10~11月頃のいずれも落葉期の後である。ミズナラやコナラ等はこの貯蔵炭水化物が増加する前に「ナラ枯れ」によって地上部が枯れる。一方、シイ・カシ類では「ナラ枯れ」で地上部が枯れる前に貯蔵炭水化物が増加する(図2)。このようなことからすればミズナラやコナラ等の落葉広葉樹はシイ・カシ類の常緑広葉樹に比べて萌芽更新は難しいといえる。
さらにミズナラやコナラなどにとってゆゆしき問題は、健全なミズナラやコナラの根には多数形成されている菌根が「ナラ枯れ」した根では観察されないこと、また「ナラ枯れ」被害地では、菌根菌の子実体の発生が少ないといわれていることである。つまり、これらの観察事例はナラ枯れしたミズナラやコナラなどは根の生長点細胞への貯蔵養分の篩部転流が阻害されることによって根の伸長が停止し、同時に水分やミネラルなどを吸収する細根の消失に伴い菌根菌との共生機能が喪失することを示唆するものである。細根の消失は地下部の生死の判定基準である。
老齢過熟木では萌芽更新力が弱く、萌芽が生き残るのはきわめて厳しいが地際部へのカシナガの集中アタック、とくに地下部へのカシナガによるナラ菌の侵入を防ぐことができれば地上部(樹冠部)が枯れたとしても萌芽更新は少なからず可能であろう。
上述したナラ菌による地上部や地下部の枯死メカニズムに関してはそれなりに理解できるが今後さらなる事象の積み重ねによる科学的実証が必要であることは云うまでもない。
松枯れの元凶「マツノザイセンチュウの恐るべき戦略」
1.マツノザイセンチュウはどのようにして土壌中から樹体組織の樹脂道や放射組織という生息域への転換をなし得たか?
マツノザイセンチュウは分子系統学的にはカリブ海沿岸諸島や南米でヤシ類を枯らす赤色輪腐病(red ring disease)の病原体であるココヤシセンチュウ(B.cocophilus)や土壌生息性のグループと同一分岐群に属していてマツノザイセンチュウがどのようにして土壌中から樹体の樹脂道や放射組織という生息域への転換を成し遂げたかについては実に興味津々たるところである。
マツノザイセンチュウ(Bursaphelenchus xylophilus)は、糸状菌食性の植物寄生性線虫である。本来、植物寄生性線虫は土壌中にいて根に寄生し、地上部の萎れなどの生理障害を引き起こす性質をもっているが、Bursaphelenchus属の線虫はもともと昆虫に便乗し、生息場所を移り変えて生活する昆虫嗜好性の線虫である。このことからすればマツノザイセンチュウがマツノマダラカミキリに便乗するために土壌中から樹体組織という生息域への転換はあり得て決して不思議ではないが、ここで本線虫が何故土壌中から樹体内の樹脂道や放射組織という生息域への転換を成し得なければならなかったかをマツ材線虫病の病状進展とマツノザイセンチュウの樹体内での行動生態から紐解いてみよう。
マツノマダラカミキリによって運ばれてきたマツノザイセンチュウは、自らの宿命ともいえる根に寄生するためにマツの強力な抵抗をうまくくぐり抜けて若枝のマツノマダラカミキリの後食痕から樹幹部を経て素早く根に移動する。そして根の樹脂道や放射組織を生息場所として定着、交尾・産卵し、繁殖を繰り返す。孵化した多数のマツノザイセンチュウは仮道管と放射組織をジグザグ状に徘徊し、分布域を広げる。そのため生息場所およびその周辺部の樹体組織は、マツノザイセンチュウによる組織柔細胞の変性・壊死の拡大によって凄まじく破壊される。そして根に蓄積されたデンプンなどの貯蔵物質の根の生長点細胞への転流が阻害されて根の伸長が停止し、細根が消失する。その結果、根の水分やミネラルなどの養水分吸収機能と同時に外生菌根菌との共生機能が損壊して通水が完全に止まる。細根の消失は根系の生死の判定基準であり、根の伸長が停止し細根が消失すればマツは“枯れる”!
完全な通水の停止によって樹体の水分状態が悪化し、光合成機能の低下が始まると樹体全身に移動分散したマツノザイセンチュウはその機を逸せず爆発的な増殖を開始する。同時に寄主であるマツは次第に衰弱し、マツノマダラカミキリの産卵が始まる。樹体内で激増するマツノザイセンチュウは寄主の枯死による生息環境の悪化に伴い生活環を増殖型から分散型に切り替え、マツノマダラカミキリの蛹室直ぐ側の仮道管や樹脂道内で待機する。そして、新たな生息地(健全木)に運んでもらうためにマツノマダラカミキリが蛹室で成虫になるや否や口針や消化器官がなく体表が粘着物質で覆われた耐久型幼虫となり、一気にマツノマダラカミキリに乗り移る。
これが根に寄生したマツノザイセンチュウが早期に地上部に移動分散する行動の意味するところであり、マツノマダラカミキリに乗り移るためのマツノザイセンチュウの緻密な行動戦略である。その戦略によってマツノザイセンチュウは土壌から樹体組織へというまさしく種の命脈をかけた生息域の転換を成し遂げたのである。
2.マツノザイセンチュウは根の癒合部位を経て根が連結した健全木を枯らす!
上述のようにマツノザイセンチュウはマツノマダラカミキリの生存には直接寄与しないがマツに対して病原性を持ち、間接的にマツノマダラカミキリの繁殖戦略に寄与する条件的共生関係に共進化させ、マツノマダラカミキリに乗り移り、移動分散を依存して生活していることは理解できたとしてもここで問題になるのは根に寄生するマツノザイセンチュウは根の癒合部位を経て移動し、根が繋がった新たなマツを枯らすということである。つまり、ある年にマツノザイセンチュウによる枯損木が発生すると翌年、その枯損木やその伐根の周囲にある健全木が枯れ、翌々年、その枯損木や伐根の周囲の健全木がまた枯れる。言うなれば最初に発生した枯損木やその伐根を中心にその周辺の健全木が枯れて5,6~10本の小集団的な枯損被害があちこちに発生し、それが次第に蔓延拡大して数年でマツ林は崩壊するということである。この枯損被害拡大パターンが現行の予防法や駆除法を駆使しても容易に被害は終息せず現状のままでは数年でマツ林が壊滅し、大径木ではシロアリが大発生する原因ともなっている。
ここ数年、島根県出雲市、千葉県館山市九十九里浜、茨城県大洗町、新潟県胎内市、長野県など地域によっては散布薬剤の飛散問題等によって有効な空中散布の中止を余儀なくされ、それに代わる防除対策の失敗のみならず上述した根の癒合による被害拡大によって松くい虫被害が再び激増しているところがある。千葉県九十九里浜の海岸マツ林(写真)では永年守り育ててきた豊かな生物多様性を持つ白砂青松の松原がわずか数年で再び砂丘に戻り、砂防にかけた人々の途方もない情熱と長年の苦労、県民の多額な税金が水泡に帰した。松を守るかどうかは地元の選択!枯れてからでは遅い。枯れる前に守る!世界文化遺産の三保の松原は守れるか!
- 千葉県九十九里浜の海岸松林

棚田 過疎化と棚田保全対策
「日本の棚田百選」の選定公表と相前後して、多くの地区での棚田のオーナー制度が発足、その保全に大いに貢献している。しかしながら過疎化と高齢化によりボランティアの農作業従事者の確保が深刻な問題となりつつあり、何か新たな対策が必要ということを痛感する。農林水産省は2000年より中山間地域等直接支払制度を発足、01年度には全国63万haを対象に514億円(平均10a当り8100円)が助成されている。また07年度からは農地・水・環境保全向上対策として環境直接支払制度も導入されるようで、将来棚田の景観維持も対象となる可能性もある。このような国による財政的な措置は棚田の保全に有効であるが、十分とは言えない。ともかく、棚田の耕作者が安心して暮らせるための安定した収入が保障されるよう、国の助成やオーナー制度のほかに収入を増やす何らかの手段が必要と思われる。対象者や徴収の方法については専門的な立場からさらに検討を要するが、棚田の景観をを鑑賞するための鑑賞料を徴収する制度もその一助になるのではないだろうか。99年に棚田百選が公表されて以降、写真撮影を目的とした訪問者も多くなっている。
選定された全国134の棚田のすべてを訪れ、その写真を紹介しているホームページもある。また観光バスを利用した撮影ツアーも多く、柵田の畦畔にー列に並んで三脚を立て撮影する写真など頻繁に紹介されている。収穫祭などのイベントに参加する人々も大半はカメラマニアであり、ほとんどの人(私もそのー人だが)がその地区の特産物や土産物を購入することなしに、ただ、柵田を眺め写真を撮影し、農家の人達に迷惑をかけて帰るだけである。すでに地域によっては視察の申し込みを受け、必要な費用を徴収している団体もある。それぞれの棚田によって、どのような形で徴収するか検討の余地はあるが、少なくとも撮影を目的として訪れる人からは、入漁料と同じような感覚で一定料金を何らかの方法で徴収してもいいと思われる。それによって得られた収入が柵田の保全に有効に使用されるなら、私は喜んでその徴収に応じたい。
(農業共済新聞より)

- 03-5209-2512

 松永 和紀(科学ジャーナリスト、FOOCOMNET編集長)
松永 和紀(科学ジャーナリスト、FOOCOMNET編集長) 廿日出 正美(静岡大学名誉教授)
廿日出 正美(静岡大学名誉教授) 田畑 勝洋(岐阜県立森林文化アカデミー客員教授)
田畑 勝洋(岐阜県立森林文化アカデミー客員教授) 梶原敏宏(元 緑の安全推進協会会長)
梶原敏宏(元 緑の安全推進協会会長)